警察のサイバー専門捜査員獲得についての記事が出ていました。
this.kiji.is
民間からの経験者採用でサイバー捜査員を募集する警察が多い中、埼玉県警はIT資格を持つ大卒、大卒見込みの採用枠「サイバー犯罪捜査Ⅰ類」を設けている。技術力と捜査力を兼ね備えたサイバー捜査員のエースを育てるためだ。2017年の試験に合格し、18年から勤務する第一号の警察官は今、警察署にいる。専門枠だが、警察学校で柔道などを教わるのは他の警察官と同じ。交番や警察署勤務を経るのも同じで、専門能力を発揮するまでには3~4年掛かるという。 園田さんは「技術者に幸せなキャリアパスを想像させてほしい。警察官としての姿を重視され、『交番勤務から』となると、優秀な技術者を集めるのは難しいのではないか」と首をかしげた。
園田さんは、年収数千万円の待遇で迎える企業も少なくないとして「人材確保は世界との闘い。良い技術者はグーグルなどの外資系企業に行ってしまう。警察が闘うにはつらいものがある」と指摘した。
(共同通信記事より引用)
◆キタきつねの所感
以下、日々努力されている警察関係の方に悪気はないのですが、、、
民間との人材獲得競争で考えるならば、警察組織の上層部の方は、サイバー枠の教育プランについて再検討した方が良いのではないでしょうか。専門官に入って数年間交番勤務の必要性はあるのでしょうか?伸び代がある数年間を棒に振るだけだと思います。
でなければ、内部育成を諦め、サイバー分野の予算獲得に注力し、外部サービス活用、つまりアウトソーシング主体で考えた方が良いかと思います。
もっと言ってしまえば、優秀な新卒人材の獲得だけでなく、育成した人材あるいは、現在教官となっている中核人材まで、それこそ外資系企業から引き抜かれていく将来も考えた方が良いのではないでしょうか?
(セキュリティ分野の)優秀な人材獲得が、世界との戦いと認識しているのであれば、教育・キャリアパスのみならず待遇面(給与)でも、一般の警察官と同じ・・・としては、専門組織を維持・拡大していく事が難しいのではないか・・と懸念します。
記事ではサイバー戦線の生の情報(1次情報)に触れるのが警察の魅力というような事が書かれていましたが、私でしたら、少し経験を積んだ後に、自分を外資系企業に売り込む事を考えます。(外資系ならまだ良いのですが、ハッカー、あるいは他国のスパイ組織(ダーク側)に高い報酬を餌に、内部情報を持って引き抜かれたら・・・と考えると恐ろしいものがあります。
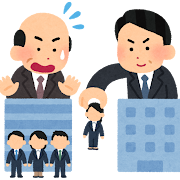
更新履歴